| 3.メカボックスの加工その2 |
|---|
 セレクターカムがすり減ってきたのとセレクタープレートの歪みによってセミフルの切り替えは出来なくなりましたが、この様なカムでセイフティーの役目は果たしております。厚さ2mmのアルミ板で出来ています。<Fig・19>
セレクターカムがすり減ってきたのとセレクタープレートの歪みによってセミフルの切り替えは出来なくなりましたが、この様なカムでセイフティーの役目は果たしております。厚さ2mmのアルミ板で出来ています。<Fig・19>また、空回りを防ぐために0.5mmのピアノ線を差し込んでかしめてあります。ピアノ線の長さは5mm位です。 |
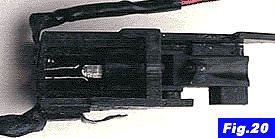 スイッチボックスです。<Fig・20>
スイッチボックスです。<Fig・20>ここもマガジンキャッチと干渉したので前側を削ってあります。 スイッチの端子を作り直してあるのがお分かりでしょうか? フルオートのみならば比較的簡単に(それこそマイクロスイッチのみで)出来ますのでこのあたりのスイッチボックスの加工は必要なくなります。面倒な方はフルオートのみにしてしまうのも良いかも知れません。 |
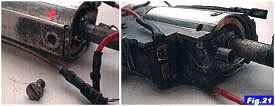 スイッチボックス周辺のアップです。(見にくい写真で申し訳ないです。)
スイッチボックス周辺のアップです。(見にくい写真で申し訳ないです。)今回の工作の一番の難関がこの周辺のすり合わせでした。スイッチボックス・マガジンキャッチ・タペットプレート・コード・左右合わせのネジなどが狭い中にひしめき合っております。 あっちは何ミリ、こっちを何ミリと言った現物合わせにて何とか押し込みました。 また矢印のところに細いひび割れが見えますでしょうか?これが進むとピストン停止位置がずれ、お亡くなりになります。 |
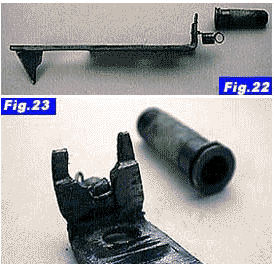 タペットプレートです。<Fig・22・23>金属製のカスタムパーツを切断し、長さを調節して新たにノズルとかみ合う部分を作ります。ノーマルのタペットプレートスプリング取り付けステーを切り取りタペットプレートスプリングをノズルの直下に取り付けられるように加工します。<Fig・22、23>焼きの入っていない軟鉄らしく、切断・曲げ加工などは比較的楽に出来ました。
タペットプレートです。<Fig・22・23>金属製のカスタムパーツを切断し、長さを調節して新たにノズルとかみ合う部分を作ります。ノーマルのタペットプレートスプリング取り付けステーを切り取りタペットプレートスプリングをノズルの直下に取り付けられるように加工します。<Fig・22、23>焼きの入っていない軟鉄らしく、切断・曲げ加工などは比較的楽に出来ました。また、ノズルの加工ですが、金属製のノズルを延長しています。金属製ノズルの先端の絞ってある部分を切り取って、中に真鍮製のパイプを継ぎ足し、ノーマルのノズルの先端部分を取り付けます。一応その継ぎ足した部分に紙を巻いて、瞬間接着剤を染み込ませて補強にしています。 この紙に瞬間接着剤というのが結構強度が出ますので私は愛用しています。 |
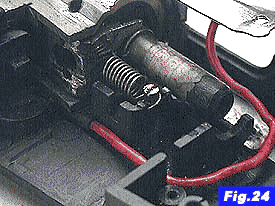 タペットプレート付近をレシーバーに組み込んだ所です。<Fig・24>と共にご覧になるとお分かりになると思います。タペットプレートスプリングは、中央の突起に引っかけてテンションを与えます。(<Fig・04>参照)
タペットプレート付近をレシーバーに組み込んだ所です。<Fig・24>と共にご覧になるとお分かりになると思います。タペットプレートスプリングは、中央の突起に引っかけてテンションを与えます。(<Fig・04>参照)この写真からもノズルの延長部分が分かると思います。根本は金属製カスタムパーツ、先端部はノーマルノズルです。つなぎ目の補強の様子がお分かりでしょうか? 多分BB弾との摩擦ですり切れてしまうと思っていましたが予想外に丈夫でした。 タペットプレートスプリングはタペットプレートが前進位置の時でも多少のテンションを残す様に調整して下さい。 |
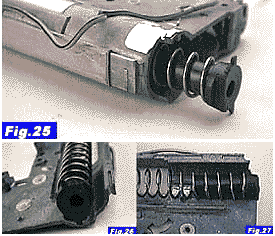 メカボックス後端はこの様になっています。<Fig・25・26・27>
メカボックス後端はこの様になっています。<Fig・25・26・27>メインスプリングのテンションはレシーバーの方で受け持つことになります。もう少し内部の幅に余裕があれば、メカボックス自体にまかせるのですがこの様な方式になりました。ただ、組立・分解が面倒なだけで、こちらの方は耐久性などに問題はないようです。 スプリングガイドとメカボックス後端ををレシーバーの構造にあわせて写真のように削ります。 丁度<Fig・25>に写っていますが、コードの取り回しもこの様にメカボックスにくぼみを付けて通してあったりします。このコードのせいで、レシーバーの左右を合わせるネジを一本追加しています。 今見てみると、メカボックス最後部を通せば良かったような気がします。う〜ん「後悔先に立たず。○○○は常に立たず。後に立つだけ後悔の方がまし」ですな。 |
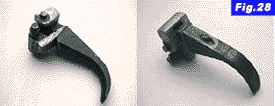 トリガーはノーマルの物ではなく写真の様にノーマルの根本と、ジャンクパーツのトリガーをあわせました。本来のスコーピオンの物には似ていませんが、根がいい加減なせいか私はあまり気になりません。 トリガーはノーマルの物ではなく写真の様にノーマルの根本と、ジャンクパーツのトリガーをあわせました。本来のスコーピオンの物には似ていませんが、根がいい加減なせいか私はあまり気になりません。初めは2mm厚のアルミ板から作ったのですが強度不足で曲がってしまいました。 |
 次にバレル回りです。チャンバーはスコーピオンノーマルの物、インナーバレルはバレルは東京マルイ製コッキングハンドガンの「グロック17L」HOPから取りました。また、アウターバレルはジャンクパーツから適当な物を使っています。
次にバレル回りです。チャンバーはスコーピオンノーマルの物、インナーバレルはバレルは東京マルイ製コッキングハンドガンの「グロック17L」HOPから取りました。また、アウターバレルはジャンクパーツから適当な物を使っています。またインナーバレル外周には絶縁のため一応セロテープを巻いてあります。 バッテリーはSONY製ガム電池(1、2V400mA×5本で6V400mA)をバレル外周に巻き付けるように取り付けました。充電はコッキングハンドルを引き、エジェクションポートからコードを引き出して行います。 |
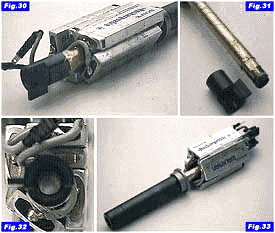 このあたりはレシーバー・コード・バレル・メカボックスとの芯だし・ノズルの給弾・エア漏れ対策など、エアガンとしての要の部分です。慎重に現物合わせをしていって下さい。
このあたりはレシーバー・コード・バレル・メカボックスとの芯だし・ノズルの給弾・エア漏れ対策など、エアガンとしての要の部分です。慎重に現物合わせをしていって下さい。このあたりのパーツとメカボックス・レシーバーとのすり合わせが一番こたえます。結局コードや、ホンの数ミリの寸法の違いから上手く行かないことも多いと思いますが、頑張って下さい。 バッテリーについては本当は6本内蔵させたかったのですが、なんとしても無理でした。結果的には6V(5本分)で十分な発射速度が得られましたが少しでもロスがあると動かない可能性もあります。 また電池の半田付けはあまり電池に熱が伝わりきらないように上手にやって下さい。W数の高いはんだごてで短時間にやるのがよいようです。 |
|
基本的に電動M16のグリップ部分と同じ構造になっております。 モーターのコードはグリップ内部の仕切り板に開いた穴を通ってモーターの端子へ向かっています。 底板の取り付けは、グリップにナットを埋め込んで底にねじ込む形を取りました。 底板と、モーターへの電極がショートしないように絶縁しておいて下さい。絶縁には「熱収縮チューブ」が便利です。 またグリップの内側にはモーターの遊ぶ隙間があるとかなり具合が悪いです。ですので、グリップの厚みを付ける加工をするときに一緒にモーターが固定されるようにプラリペアを流し込みましょう。取りあえず、円周方向に回転しなければOKです。 |
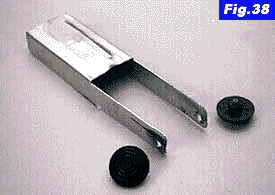 エジェクションポートカバーです。0.5mm厚のアルミ板から製作しました。この部品はエジェクションポートの所で、メカボックスのシリンダーヘッド固定ネジ<Fig・21左側写真のネジ>の抜け止めとしての要素もあります。
エジェクションポートカバーです。0.5mm厚のアルミ板から製作しました。この部品はエジェクションポートの所で、メカボックスのシリンダーヘッド固定ネジ<Fig・21左側写真のネジ>の抜け止めとしての要素もあります。また、この部品を金属製にするだけで随分とリアルになる物です。ノーマルのスコーピオンを使っている方は、エジェクションポートにアルミシールを貼っても良いかも知れません。 コッキングハンドルはこの部品に直接ネジを立ててみましたが当然の事ながら直ぐ取れてしまいました。 |
 細かなところですが、トリガーガードです。セクターギアがギリギリの所まで来ているのでトリガーガードの根本に十分な強度が残せませんでした。そこで少々みっとも無かったのですが、メカボックスに直接ネジを立て、固定しました。
細かなところですが、トリガーガードです。セクターギアがギリギリの所まで来ているのでトリガーガードの根本に十分な強度が残せませんでした。そこで少々みっとも無かったのですが、メカボックスに直接ネジを立て、固定しました。
|
メカボックスの加工その2はこれで終了
ここまで来たら実射性能データ「4・まとめ・実射」が見たい方はこちら。
初心に戻って「1・全体の構成2・レシーバーの加工」に戻る方はこちら。
もう一回「メカボックスの加工その1」を見ておこうと言う方はこちら。
取りあえず「GUN SMITH」のHOMEに戻りたい方はこちら。
HOME/C/Plus BBS/Free-Market R/WARNING/COSTOM/TUNING/FRENDS
TOOLS/OLDTIME/INTRO/TOYGUN FAQ/TRAVEL/LINK/DIARY/SHOP/MAIL