電動ブッシュマスターVol.1
ブッシュマスター製作法は全部で3部構成になっております。
では製作に入ります。
| 1.全体の構成 |
|---|
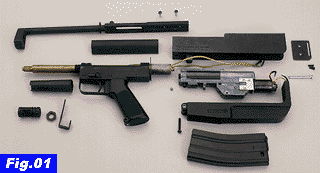 ブッシュマスターはM−16をベースに開発されたブルパップハンドガン(ブッシュは一応ハンドガンの範囲に入るようです)です。
ブッシュマスターはM−16をベースに開発されたブルパップハンドガン(ブッシュは一応ハンドガンの範囲に入るようです)です。しかし実銃がM−16ベースとはいえ、電動メカボックスを納めるには大変な苦労がありました。 また、このエアガンのベースとなったアサヒファイヤーアームズ製のブッシュマスターは今となっては非常に手に入り難く中古相場も高値安定しているようです。 さて、構成としては、Ver.2のメカボックスに関してはストローク短縮・短縮したスペースにチャンバーを新設・モーターの位置換え・フルオートオンリーのためスイッチボックス部分の撤去・メカボックス上部リブのカット等です。<Fig・1> またベースになったブッシュマスターは、外観はほぼそのまま使用しますが、後部を2cm程延長してあります。内部のBVユニットはサブチャンバーの付近で切断し、銃口先端からレシーバーにかけての構造材として使用します。グリップはマルイ製の物を使用し、その中にSONY製ガム電池(アームズに載っていた物は400mmAのデータで、今は600mmAに増量してあります)を仕込みます。 |
| 2・レシーバーの加工 |
|---|
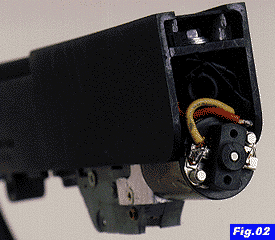 ロアレシーバーをはずした状態でのメカボックスの収まり方を示しています。<Fig・2>
ロアレシーバーをはずした状態でのメカボックスの収まり方を示しています。<Fig・2>この様に幅・長さともにぎりぎりに収まっています。(ぎりぎりと言っても長さだけは2cmほど延長してあります)この写真から、アッパーレシーバーを2mm厚のABS板で延長しているのがお分かりと思います。 またアッパーレシーバー最後尾の円形のパーツはMP5のフロントスイベルリングです。 これは組み立てたときに後ろからネジでメカボックスとロアレシーバーを固定するのですが、メカボックスの後ろが軸線に対して尻下がりにならないようにするためにこのリングで固定用ネジをつり上げています。 |
 レシーバーの延長について詳しく説明いたします。<Fig・3>
レシーバーの延長について詳しく説明いたします。<Fig・3>ストロークの短縮などでメカボックスの全長を押さえても結果的に2cm程ストレッチしました。まずアッパーレシーバーは2mm厚のABS板にて延長してやりました。尚、コッキングレバー後部のカバーも追加してあります。 次にロアレシーバーですが、一度切り放した(このとき、ロアレシーバー側面中程の一段細くなっているところも切り放します)後に1mmABS板にて延長しました。この部分はモーターの一番直径の大きな所がくるので、強度的に不安ながらその様にいたしました。しかしながら、モーター部以外はスペースが余りますので、一番強度の出る「レジン」にて裏打ちをしたのと、結果的にモノコックになったので結構丈夫に仕上がりました(肉厚のうすい所はその直ぐ裏にモーターなりのパーツが接触している事もあります)。 またモーターの後端部がはまるように10mm程の穴も開けておきます。 |
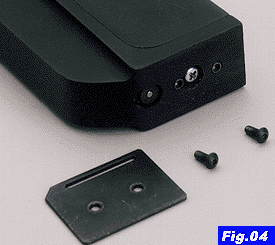 ロアレシーバーとアッパーレシーバー・メカボックスとの結合の様子です。<Fig・4>
ロアレシーバーとアッパーレシーバー・メカボックスとの結合の様子です。<Fig・4>この写真からもメカボックス固定ネジと、モーター後端部の様子がお分かりと思います。この部分はスリング用の鉄板がはまりますのでこの様にネジが露出していても目立たないのでいい感じでした。 ロアレシーバーの造形も良く見えます。特に側面のRは目立ちますので注意深く造形しましょう。私は箱組と、裏打ちが終わった後、プラリペアを盛りつけ、9mmの真鍮パイプにセロテープを貼った棒で押しつけてRを出しました。この方法も結構綺麗にRを付けることが出来ます。 |
以上でVol.1を終わります。
そのまま次の「3.メカボックスの加工」に進む方はこちら。一寸跳ばして「4.仕上げ 5.完成」に行っちゃう方はこちら。
取りあえず「GUN SMITH」のHOMEに戻りたい方はこちら。
HOME/C/Plus BBS/Free-Market R/WARNING/COSTOM/TUNING/FRENDS
TOOLS/OLDTIME/INTRO/TOYGUN FAQ/TRAVEL/LINK/DIARY/SHOP/MAIL